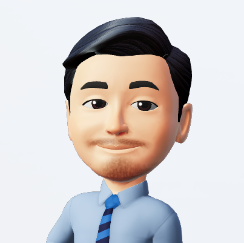青物が釣れる時期,場所,時間帯について
青物が釣れる時期について
ショアから青物が釣れる最盛期は10月~12月です。この時期であればどこの防波堤でもチャンスはあると思います。4月~6月も釣れるますが,秋に比べると劣ります。
青物が釣れる場所について
青物が釣れる場所かどうかを判断するためには,ベイト(イワシ,コノシロ,サッパ,小アジ)がいるかどうかを確かめることが大切です。青物狙い以外の釣り人や地元民からも情報を収集することができます。特にイワシが岸際を大群で速く泳いでいる場所は,青物が回遊していることが多くチャンスが大です。青物に追われて岸際を泳いでいることが多いからです。また,青物はコノシロが好物なのでコノシロがついているサーフも狙い目となります。
また,一般的には水深があって潮通しが良い場所が青物を狙うには良いとされていますが,水深が10m以下で潮通しも悪い場所でも,ベイトが溜まっている場所ならチャンスはあります。湾奥の浅場にベイトが追いこまれて,ナブラが湧くこともよくあります。
青物が釣れる時間について
ショアから青物が一番よく釣れる時間帯は,夜明け時です。いわゆる「朝まずめ」です。潮汐表にある「日の出」の時間よりも,30分位前には釣り場に到着するようにしましょう。日の出の30分位前から日の出から30分後位までがチャンスタイムとなります。この時間帯にどれだけキャストするかが,青物の釣果につながります。水温が低くなっている真冬は,日が昇り水温が上昇したタイミングで魚の活性が上がることもあります。
夕方,日没前の1時間位前から暗くなるまでもチャンスタイムで,いわゆる「夕まずめ」です。
ショアから青物を釣るために
青物を釣るために重要なことは,青物が釣れる時間帯に,釣れる場所で,どれだけ多くキャストするかです。まずは,自宅から無理なく通える釣れそうなポイントへ,朝まずめの時間帯に足繁く通うことから始めてください。偵察だけでキャストしなくても良いので,とにかく色々な場所の朝まずめの状態を知ることが大切です。最盛期は,朝まずめにナブラが湧いていることもよくあります。平日は偵察のみで,休日に偵察の情報を元に釣行するのも良いでしょう。
また,情報収集も大切ですが,他人やネットからの情報に頼るのではなく,自ら足を運んで得た情報で釣ることを習慣づけることも大切です。そうすれば,ベイトの動向も予測できるようになり釣果は伸びると思います。ベイト(特にイワシ)の居場所は,すぐに変わってしまうので他人からの情報はあてにならないことが多いです。

良型の青物をバラさないために
先にも述べていますが,初心者の方にも良型の青物がヒットする可能性は十分にあります。しかし,せっかくヒットした良型の青物も,バラしてしまっては元も子もありません。
よく,「逃した魚は大きかった」と言いますが,逃した魚がたまたま大きかったのではありません。「大きな魚ほど,逃しやすい」のです。
それでは,良型の青物をバラさずにキャッチするために必要なことについて解説します。
準備
この記事の最初に,良型の青物をキャッチする(釣り上げる)ためには,それなりの準備が必要で,準備とは,ロッド,リール,ラインシステム,スナップ,ランディングツール,フック交換,これらのタックル全般と,そのメンテナンスです。と書きましたが,その準備を怠ると良型の青物をバラしてしまう確率が高くなります。
最低限,「ランディングツール」,「ラインシステム」,「フック」は,対青物用にしてください。
ランディングツール
足場の高い堤防で80㎝以上のブリを抜き上げることはできません。80㎝オーバーの青物がヒットした時を想定したランディングツールを準備してください。タモの場合はタモ網の深さが80㎝以上あるものを用意してください。そもそもタモに魚が入らないのであればランディングはできませんので,青物用のランディングツールの準備は必須条件です。
ラインシステム
例えば,エギング用のPE0.6号にリーダー2号のラインでブリクラスがヒットした場合,キャッチするのは相当難しいでしょう。また,PEラインを2.0号,リーダーを40LBにしたとしても,強度の低いノットでは意味がありません。強度の高いノットをマスターすることも必要です。私は,PEラインとリーダーはFGノット,スナップにはダブルクリンチノットにしています。
ノットの方法については,こちらを参照してください。「VARIVASノット大図鑑」
フック
元々シーバス用に開発されたルアーで青物を狙うこともあります。シーバス用のルアーのフックは細いため,良型の青物がヒットすると伸ばされてフックアウトしてしまいますので,交換が必要です。純正のフックサイズが#6~#5のルアーの場合は,Hタイプのフックに交換した方が良いでしょう。#6のMHでは,良型青物に伸ばされてしまいます。
フッキングについて
青物をバラさないためには,しっかりとフッキングを決めることが大切です。フッキングはロッドを上に向けてしっかり決めるのが鉄則です。向こうアワセではフックは引っかかっているだけで,食い込んでいません。特に青物用の太軸のフックを食い込ませるためには強いアワセが必要です。
初心者の方がせっかくヒットした青物をバラしてしまう要因の一つが,フッキングが決まっていないことです。突然の青物の強烈な引きにびっくりして,アワセを入れないままやり取りを開始してしまい,ランディング前のエラ洗いでバレるパターンが多いです。
青物がルアーにバイトした時,しっかりと口の中にルアーが入っていなかったとしても,アゴ付近にかかったフックを上方向にアワセを入れることで,しっかりとフックを食い込ませることができます。アタリを感じた時,ルアーのフックが魚の頭側(上側)に刺さっていることはほぼありませんので,フッキングは上方向にしっかりと決めることが鉄則です。
ジャークの途中でアタリがあった時も,とりあえずジャークと同じ方向でアワセを入れてから,再度上方向に追いアワセをしっかり決めてください。よく,「サワラは口が柔らかいので,ドラグは緩めで」と言われる方がおられますが,フッキングの時のドラグはキツめの方が良いです。そもそも,フッキングの時点でサワラかブリかを見極めることは困難です。青物を狙っていてアタリがあったら,とにかく鬼アワセしてください。
フッキングの際にドラグがジャーっと滑るようであればフッキングは決まっていません。時々,メディアでも見かけますが,ボートでヒットしたサワラをランディング直前のエラ洗いでバラすシーン。この原因のほとんどがフッキングが決まっていないことです。最初からドラグの設定がゆる過ぎるか,向こうアワセのまま追いアワセを決めていないかです。
ドラグの調整について
フッキング時のドラグはキツめの方が良いと書きましたが,ランディングする時(魚が手前まで寄ってきた時)のドラグは,少し緩めの方が良いです。
なぜ,緩めの方が良いかというと,なるべくエラ洗いをさせないためです。釣り人(ロッド)と魚(フック)の距離が近い時のエラ洗いはバラしの確率がグンっと上がります。とは言っても,ラインテンションは絶対に緩めないようにしてください。岸際で魚が走った際に,エラ洗いはしない程度にラインが出るけど,走らせすぎないといった,ドラグのさじ加減が必要です。エラ洗いしたとしても,ガチガチのドラグよりも,適度にドラグを緩めた方がラインテンションも抜けにくく,バラす確率もグンっと下がります。
また,ブリは空気を吸わせてからランディングした方がタモに入れやすいですが,サワラはなるべく海面から頭を出させないままランディングすることがコツです。サワラには浮き袋がありません。浮き袋のあるブリは,空気を吸って弱ると海面で魚体が横を向きますが,サワラは,完全に弱りきると,海面で頭だけ出して縦になります。縦になった90㎝越えのサワラを一人でランディングするのは,かなり難しいです。

その他,準備した方が良いもの
(1)クーラーボックス
クーラーボックスは青物が入る大きさの物を選んでください。理想は内寸80㎝以上ですが,頭と尾を切って入れるなら内寸60㎝でも良いでしょう。できれば発泡スチロールではなくクーラーボックスにした方が良いです。発泡スチロールは保冷力が弱く,フタもしっかりと閉まらないので,車内で溶けた氷の水がこぼれることもあります。魚の血が混ざった水が車内で溢れかえったら最悪です。
(2)水汲みバケツ
良型青物は,アジなどの小型の魚に比べると,締めた時の流血量が多く,釣り場を汚してしまうこともあります。釣れた魚を締めた際の血は,水汲みバケツを使用して洗い流しましょう。ブラシも一緒に持参すると,掃除が楽です。
(3)ハサミ,ナイフ
釣れた魚を締める際に必要です。ハサミで延髄を切って締める場合は,強力なタイプが良いです。
(4)フィッシュグリップ
釣れた魚を掴む時に必要です。アジングで使用する小型のタイプでは良型の青物を掴むのに不十分なので,大型魚用フィッシュグリップを用意された方が良いでしょう。私は,ガーグリップをブリに使用して折ってしまったことがあります。
(5)プライヤー
ルアーのフック交換や,釣れた魚のフックを外す時に必要です。釣れた青物のルアーのフックは,絶対に素手で外さないようにしてください。魚が暴れた際にフックが手に刺さる危険があります。
(6)ストリンガー
釣れた魚を一時的に生かしておいたり,締めた後の血抜きに必要です。良型の青物は水汲みバケツに入らないので,ストリンガーで血抜きします。青物をぶら下げても大丈夫なものを選ぶことが大切です。重たいものをぶら下げると抜けてしまうものもあるので注意してください。青物が一番釣れるチャンスタイムの「朝まずめ」に効率よく2本目,3本目を釣るためにも,ストリンガーで一時的に活かしておくことも有効です。また,青物は数分以上ファイトをして釣り上げた直後に締めるよりも,ストリンガーでしばらく安静にさせてから締めた方が美味しいとも言われています。ストリンガーで活かす時は,フックをエラに通さず下あごを貫通させてください。エラを傷つけると,高確率で弱って死んでしまいます。
(7)神経締め用ワイヤー
神経締めをしておくと,死後硬直までの時間が遅くなり,鮮度を保つことができると言われています。私も,刺身で食べる用の青物は神経締めをしています。ワイヤーは形状記憶合金タイプをおすすめします。
(8)グローブ,フィンガープロテクター
ショアジギングは,重量のあるタックルとルアーのキャストとジャークを繰り返しますので,手首や肘を痛めてしまうこともあります。私も本格的にショアジギングにのめり込んだ年に,毎日のように素手でキャストとジャークを繰り返して手首と肘を痛めました。(腱鞘炎,テニス肘)
素手でキャストするよりも,グローブを着用していた方がグリップ力が上がるため,少ない力でしっかりとロッドを振り切ることができます。ジャークも同様です。私はグローブを着用するようになってからは,手首や肘を痛めることがなくなりました。なので,ショアジギングをする時は夏でもグローブを着用します。
また,ショアジギングの場合,素手でキャストするとラインで指を切ってしまうことがあり,思いっきりキャストできないことがありますので,フィンガープロテクターを使用した方が良いですが,指先がカットされていないタイプのグローブを使えば,フィンガープロテクターの代わりにもなります。
(9)ポリ袋45L~70L
釣れた魚を入れたり,ゴミを入れるために必要です。なるべく厚手のものが良いでしょう。私は青物用の大型クーラーボックスは堤防に持って行かずに車内に置いたままにしておき,釣れた魚はポリ袋に入れて車まで運んでいます。

最後に
皆さん,「ゴミを釣り場に放置しない」や「魚を締めた血で釣り場を汚したら,流す」などのマナーを守ってショアジギングを楽しんでください。
また,ショアジギングはルアーを100m近くもぶっ飛ばす釣りです。ロッドの長さもあり,キャストの際に垂らすラインも100cmはあります。トレブルフック付きの重量のあるルアーをキャストするので,周りの釣り人との距離を取る必要があります。キャストの際には,必ず後方確認をしてください。ショアジギングの先行者がいる場合は,最低でも3m,できれば5mは距離を取ってください。特に右投げの人の右側近くには入らないようにしてください。本当に危ないです。